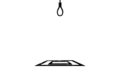要 約
死刑制度を存置する現行法制の下では、
- 犯行の罪質
- 動 機
- 態 様(殊に殺害の手段方法の執拗性・残虐性)
- 結果の重大性(殊に殺害された被害者の数)
- 遺族の被害感情
- 社会的影響
- 犯人の年齢
- 前 科
- 犯行後の情状等
を総合的に考慮し、その罪責が極めて重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合には、死刑の選択も許される。
主 文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理 由
本検察官の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれも所論のような趣旨まで判断しているものではないから、所論は前提を欠き、その余は量刑不当の主張であって、いずれも刑訴法405条の上告理由にあたらない。
しかしながら、所論にかんがみ職権で調査すると、原判決は以下に述べる理由により破棄を免れない。
1 本件は、犯行時19歳余の少年であった被告人が米軍基地内でけん銃を窃取し、これを使用して、東京及び京都では勤務中の警備員を射殺し、函館及び名古屋ではタクシー強盗を働いてタクシー運転手を射殺し、何ら落度のない4人の社会人の生命をわずか1か月足らずの間に次々と奪ったうえ、再び立ち戻った東京では学校内に侵入して金品を物色中警備員に発見され逮捕を免れるため右警備員を狙撃したが命中せず殺人の目的を遂げなかったという事案であって、第1審判決は、犯行の動機に同情すべき点がないこと、けん銃に実包を装填して携帯しており、計画性が認められること、犯行を多数回重ねており、個々の犯行の態様も、被害者の頭部、顔面等を至近距離から数回狙撃するもので残虐であること、働き盛りの4人の社会人の生命を奪った点で結果が極めて重大であること、各被害者の遺族らは精神的にも経済的にも深刻な打撃を受けたこと、本件は「連続射殺魔」事件として報道されて一般人を深刻な不安に陥れ社会的影響が極めて大きかったこと等の諸事情を考慮すると、本件は犯罪史上稀に見る兇悪事件と呼んでも過言ではなく、右の諸事情に被告人に何ら改悛の情の認められない状況を総合すれば、被告人の生育環境、生育歴等に同情すべき点があること、被告人が犯行当時少年であったこと等被告人に有利な一切の事情を参酌しても、なお死刑の選択はやむをえない旨判示して被告人を死刑に処した。
2 これに対し、原判決は、犯行の結果の重大性、遺族らの被害感情の深刻さ、社会的影響の大きさ、被告人の第1審公判における行動の異常さ等の不利な情状を総合考慮すれば、第1審判決の量刑は首肯できないではないとしながらも、死刑制度の運用を慎重に行うべきことを説いて、「ある被告事件につき死刑を選択する場合があるとすれば、その事件については如何なる裁判所がその衝にあっても死刑を選択したであろう程度の情状がある場合に限定せらるべきものと考える。立法論として、死刑の宣告には裁判官全員一致の意見によるべきものとすべき意見があるけれども、その精神は現行法の運用にあたっても考慮に価するものと考えるのである。」との見解を判示し、これを基礎として、前記の情状に被告人にとって有利な情状を併せて考慮すると、被告人に対し死刑を維持することは酷に過ぎるとして第1審判決を破棄したうえ、被告人を無期懲役に処した。原判決の指摘する被告人にとって有利な情状とは、第1に、本件犯行は一過性の犯行であり、被告人は犯行当時19歳の少年であって、恵まれない生育環境、生育歴のため、その精神的な成熟度は実質的に18歳未満の少年と同視しうる状況にあるから、少年法51条の精神を及ぼすべきであるし、また、本件犯行の原因の一端は国家、社会の福祉政策の貧困に帰せられるべきであるというのであり、第2に、被告人は第1審判決後の昭和55年12月12日Aと婚姻し、人生の伴侶を得て環境及び心境に変化が現れ、原審公判においては、第1審公判におけるような粗暴な言動を慎んでいるというのであり、第3に、被告人は犯行後獄中で綴った手記を出版し、その印税から京都事件の遺族に合計252万4,400円を、函館事件の遺族に合計463万1,600円をそれぞれ贈って慰籍の意を示し、被告人の妻Aは被告人の意を受けて京都、函館、名古屋各事件の遺族らを訪れて弔意を表したというのである。
3 死刑はいわゆる残虐な刑罰にあたるものではなく、死刑を定めた刑法の規定が憲法に違反しないことは当裁判所大法廷の判例(昭和22年(れ)第119号同23年3月12日判決・刑集2巻3号191頁)とするところであるが、死刑が人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去る冷厳な極刑であり、誠にやむをえない場合における窮極の刑罰であることにかんがみると、その適用が慎重に行われなければならないことは原判決の判示するとおりである。そして、裁判所が死刑を選択できる場合として原判決が判示した前記見解の趣旨は、死刑を選択するにつきほとんど異論の余地がない程度に極めて情状が悪い場合をいうものとして理解することができないものではない。結局、死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許されるものといわなければならない。
これを本件についてみるのに、記録によれば、本件犯行は、わずか1か月足らずの期間のうちに、東京、京都、函館、名古屋の各地で何ら落度のない社会人を4人までもけん銃で射殺し、かけがえのない生命を次々に奪って、その遺族らを悲嘆の淵におとしいれたうえ、その約半年後に更に東京で警備員を狙撃し、全国的にも「連続射殺魔」事件として大きな社会不安を招いた事件であって、犯行の罪質、結果、社会的影響は極めて重大である。犯行を重ねた動機も、あるいは先の犯行の発覚を恐れ、あるいは金品強取を企てたためであって、極めて安易に犯行に出ており、特に京都事件の犯行後は自首を勧める実兄の言葉に耳をかさず、函館に渡って更に重大な犯行を実行するに至ったもので、同情すべき点がない。殺害の手段方法についていえば、兇器として米軍基地から窃取して来たけん銃を使用し、被害者の頭部、顔面等を至近距離から数回にわたって狙撃しており、極めて残虐というほかなく、特に名古屋事件の被害者Bに対しては、「待って、待って」と命乞いするのをきき入れず殺害したもので執拗かつ冷酷極まりない。遺族らの被害感情の深刻さもとりわけ深いものがあり、右Bの両親は、被告人からの被害弁償を受け取らないのが息子に対するせめてもの供養であると述べてその悲痛な心情を吐露し、また、東京事件の被害者Cの母も被告人からの被害弁償を固く拒み、どのような理由があってもなお被告人を許す気持はないとまで述べており、遺族らの心情は痛ましいの一語に尽きる。以上のような点は被告人にとっては極めて不利な情状というべきである。
これに対し、被告人にとって有利な情状としては、原判決も指摘するとおり、被告人が犯行時少年であったこと、その家庭環境が極めて不遇で生育歴に同情すべき点が多々あること、被告人が第1審判決後結婚して伴侶を得たこと、遺族の一部に被害弁償をしたことなどの事情が考慮されるべきであろう。確かに、被告人が幼少時から母の手一つで兄弟多数と共に赤貧洗うがごとき窮乏状態の下で育てられ、肉親の愛情に飢えながら成長したことは誠に同情すべきであって、このような環境的負因が被告人の精神の健全な成長を阻害した面があることは推認できないではない。原判決が本件犯行を精神的に未熟な実質的には18歳未満相当の少年の犯した一過性の犯行とみて少年法51条の精神を及ぼすべきであると判示しているのは、右の環境的負因による影響を重視したためであろう。しかしながら、被告人同様の環境的負因を負う他の兄弟らが必ずしも被告人のような軌跡をたどることなく立派に成人していることを考え併せると、環境的負因を特に重視することには疑問があるし、そもそも、被告人は犯行時少年であったとはいえ、19歳3か月ないし19歳9か月の年長少年であり、前記の犯行の動機、態様から窺われる犯罪性の根深さに照らしても、被告人を18歳未満の少年と同視することは特段の事情のない限り困難であるように思われる。そうすると、本件犯行が一過性のものであること、被告人の精神的成熟度が18歳未満の少年と同視しうることなどの証拠上明らかではない事実を前提として本件に少年法51条の精神を及ぼすべきであるとする原判断は首肯し難いものであると言わなければならないし、国家、社会の福祉政策を直接本件犯行に関連づけることも妥当とは思われない。被告人は、本件犯行の原因として責められるべきは被告人自身ではなく、被告人の親兄弟、社会、国家等の被告人の周囲の者であるとして、自己の責任を外的要因に転嫁する態度を公判廷でも獄中の手記でも一貫して維持しているが、被告人の右のような態度には問題があるし、被告人が結婚したことや被害弁償をしたことを過大に評価することも当を得ないものである。
以上の事情を総合すると、本件記録に顕れた証拠関係の下においては、被告人の罪責は誠に重大であって、原判決が被告人に有利な事情として指摘する点を考慮に入れても、いまだ被告人を死刑に処するのが重きに失するとした原判断に十分な理由があるとは認められない。
そうすると、第1審の死刑判決を破棄して被告人を無期懲役に処した原判決は、量刑の前提となる事実の個別的な認定及びその総合的な評価を誤り、甚だしく刑の量定を誤ったものであって、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認めざるをえない。
4 よって、刑訴法411条2号により原判決を破棄し、本件事案の重大性、特殊性にかんがみ更に慎重な審理を尽くさせるため、同法413条本文により本件を原裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官筧榮一 公判出席
昭和58年7月8日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 橋 進
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 牧 圭 次